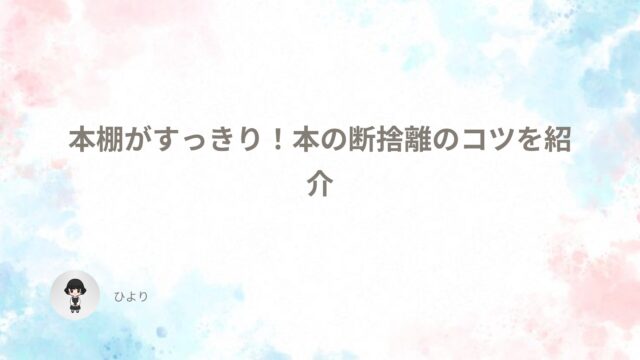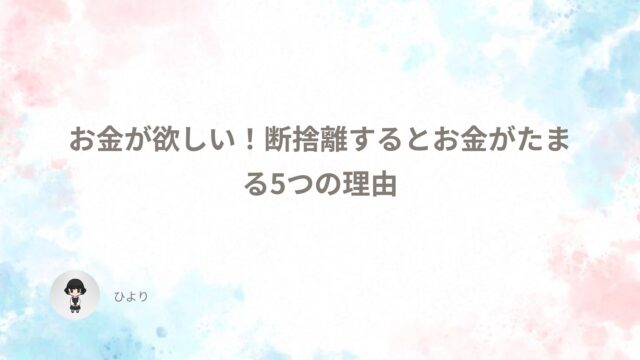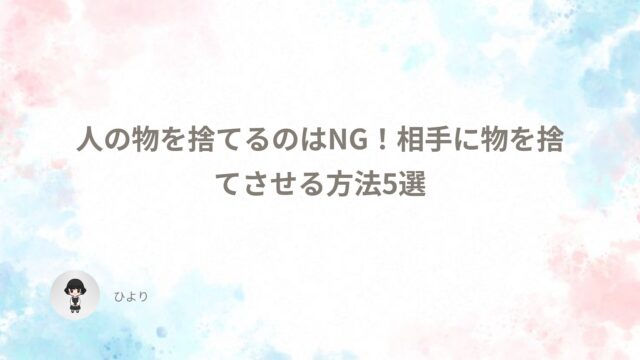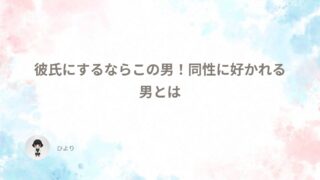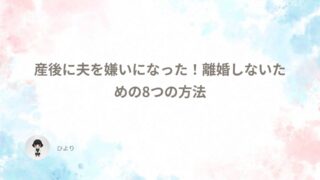家に物がいっぱい!物をため込む人の心理とは
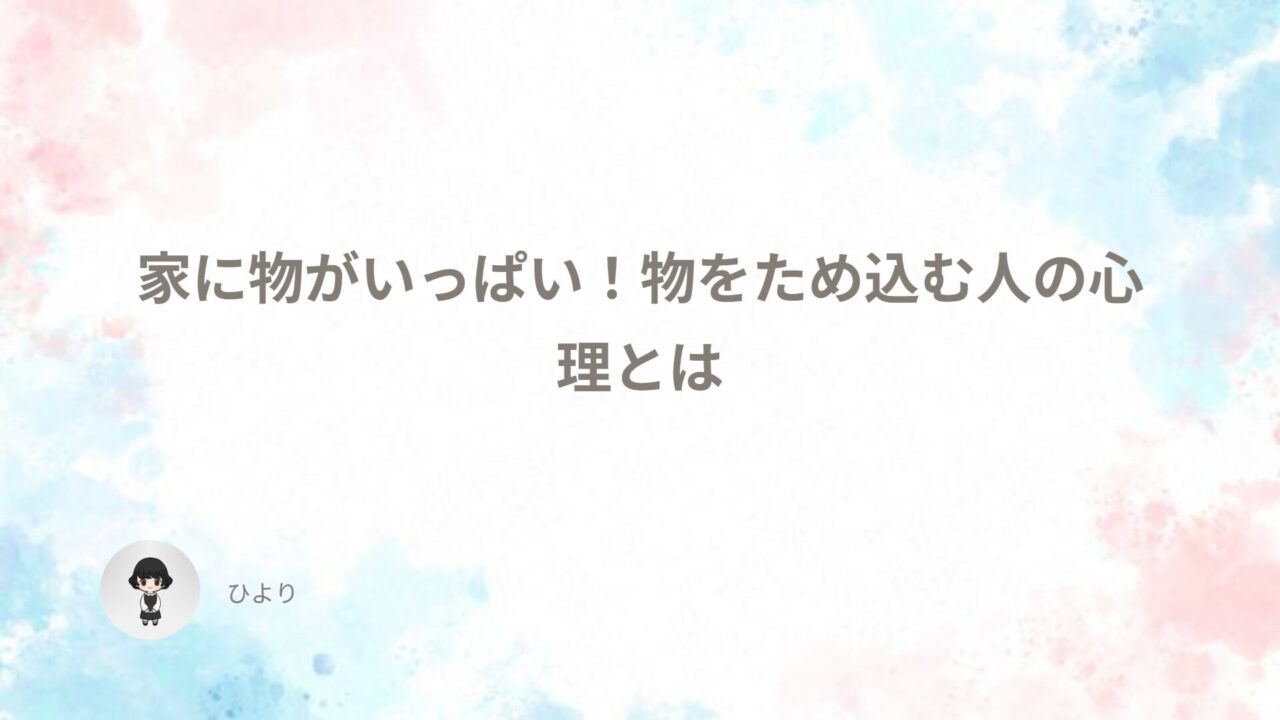
こんにちは、ひよりです。
「周りから物を捨てなさいと言われるけど、どうしても捨てられない」と悩んでいませんか?
物をため込んでしまうのには6つの理由があります。
その理由のせいで、片付けが進まなくて、家に物があふれているのかもしれません。
今回は物をため込んでしまう6つの理由と、物を捨てられる人になるための6つの方法を紹介します。
捨てることは誰でもできるかと思いきや、捨てることも能力です。
物を捨てられるようになるために、訓練をしていきましょう。
物をため込んでしまう6つの理由

物をため込んでしまうのには理由があります。
物を捨てられるようになるためには、まずどうしてため込んでしまうのか現状把握をすることが大事です。
あなたはどうして物をため込んでしまうのでしょうか。
一緒に見ていきましょう。
理由1:不安が強い
不安が強い人は、物をため込んでしまいます。
高齢者の人が物をため込んでしまうのは、若者よりも体力がないので「簡単には買えない!」「何かあったときのために」という不安が強いからでしょう。
若者でも、「突然震災がくるかもしれない」「物価高が続いているし、将来が心配」「将来のためにも物を捨てないで、お金をためておかなきゃ」という不安が強いと、物をため込みがちになります。
理由2:孤独感が強い
孤独感が強い人は、物に囲まれていることによって安心感を得ます。
物が多いほうがにぎやかな感じがしますよね。
孤独感が強い人は、孤独感をなくすためにも、「友人に連絡を取る」「積極的にやりたいことをやってみる」ということがオススメです。
理由3:自分を大きく見せたい
自分を大きく見せたい人は、ブランド物をため込みます。
「ブランド物を持っている私ってすごいでしょう」と、自分をアピールしたいのです。
そのため、ブランド物が捨てられず、ため込みが起こります。
理由4:完璧に片付けたい気持ちが強い
完璧主義の人は片付けが苦手です。
片付けに完璧はありませんし、完璧に片付けたとしても、だんだん散らかります。
その結果、「完璧に片付けられないなら、片付けない」と片付けを放棄してしまうのです。
理由5:日々が忙しくて片付けられない
毎日が忙しいと、捨てたり、片付けたりという作業ができません。
捨てる判断や片付けの判断は、想像以上に脳を使います。
日々が忙しくて脳が疲れていると、「何を捨てればいいのかわからない」という現象が起こり、捨てる作業ができなくなります。
理由6:片付けのやり方がわからない
親が片付けが苦手だと、子どもも片付けが苦手になります。
外国では片付けのやり方を教えてもらうのですが、日本では片付けのやり方は親から子へ伝えられるものとされています。
私も親の影響があるせいで、親が大切にしている布系を捨てるのはかなり苦手ですからね。
片付けのやり方がわからないのであれば、本を読んで学ぶ必要があります。
「片付けは自然とできるもの」ではありませんよ。
物を捨てられる人になる6つの方法

「物が捨てられない!」とあきらめないでください。
物を捨てられるようになるための6つの方法を実践すれば、誰でも捨てられる人になります。
方法1:日々のストレスを減らす
ストレスがあると、物を捨てることはできません。
日々のストレスを減らしましょう。
ストレス解消法はいくつかあります。
- 瞑想をする
- 散歩をする
- 読書をする
- 音楽を聴く(歌う)
- お風呂に入る
- アロマを焚く
- 趣味をする
頭を使う仕事をしているなら、肉体を使う散歩や瞑想がオススメです。
肉体の疲れには、お風呂や読書がいいでしょう。
いつも使っていない脳領域を使うことで、ストレス解消ができますよ。
方法2:捨てられる人になると決心する
「私は捨てるのが苦手だからしょうがない」とあきらめないでください。
まず、「自分は捨てられる人間だ」と自分に暗示をかけて、「捨てられる人になる!」と決意をしてください。
人は「こうする!」と決めたら、そういう風に行動していくようになります。
片付ける前に、「捨てられる人になる」と決意をしましょう。
方法3:断捨離の本を読んでモチベーションを上げる
断捨離や片づけ関係の本を読んだことはありますか?
私は断捨離の本が大好きで、自分で買ったり、図書館で借りたりしています。
断捨離の本を読むと、片付けのモチベーションが上がるのでオススメです。
私がオススメする片付け・断捨離の本はこの3冊。
<断捨離系>
<片付け系>
<片付け系のマンガ>
本はモチベーションだけでなく、片付けの基礎を学ぶことができます。
「今まで片付けのことなんて習ったことないよ」というあなた、片付け・断捨離系の本を読んで勉強をしましょう。
方法4:一日一捨に挑戦する
とうとう捨てるという実践に挑戦しましょう。
まずは、一日一捨に挑戦してください。
「一日一捨なんて、そんなのムリ!」と思ったかもしれませんが、捨てるものは特別な物でなくていいんですよ。
捨てるものは目に付いたゴミでも構いません。
財布の中のレシートを捨てるのもオススメです。
とりあえずなんでもいいから、一日一捨に挑戦してみてください。
捨てる物探しをしているうちに、捨てる脳が鍛えられて、小さなゴミしか捨てられなかったのが、だんだんと不用品を捨てられるようになっていきますよ。
方法5:捨てたものの記録を取る
一日一捨を実践したら、毎日何を捨てたのかを記録するようにしましょう。
捨てたものを記録することによって、「私、こんなに捨てられたんだ」と達成感が出ます。
記録は紙でもスマホでも、何でも大丈夫です。
私はスケジュール帳に記録していましたが、日記アプリに記録するのもいいかもしれませんね。
方法6:家に人を招く
家をキレイにするためのとっておきの方法は、家に人を招くということ。
「片づけのやる気が起きないな」と思っていても、人を招く予定を立ててしまったら、片付けをやらないわけにはいきませんよね。
仲いい友達といつもカフェでおしゃべりしてる、というのであれば、カフェではなく自宅に来てもらうようにすればいいのです。
彼氏がいるなら、お家デートをするのもいいですね。
大きな家電(冷蔵庫や洗濯機など)が壊れているなら、買い替えで業者に来てもらうというのもアリですよ。
親に来てもらうのもいいのではないでしょうか。
家に人を招く予定を立てて、その日に向かって片付けをすれば、一気に家がキレイになりますよ。
一人で片付けが難しいなら家族や友人の力を借りるべし

家に物が多すぎると、呆然となってしまって、どこから手を付けていいかわからなくなりますよね。
1人では手に負えないほど物が多いなら、家族や友人の力を借りて片づけをしましょう。
「人に見せられる部屋じゃない!」なんて言っている場合ではありません。
物が多く、不衛生の場所にいると、呼吸器の病気になる可能性があります。
また、床に置いてある物を踏んで転倒し、骨折なんてこともあります。
自分でできないことは人の力を借りることも大事。
家族や友人の力を借りて、思いっきり片づけをしてから、日々のメンテナンスは一人で頑張ればいいんですよ。
物を捨てられるようになるためにはトレーニングが必要

物を捨てるようになるためには、日々の物を捨てるトレーニングが必要です。
捨てる脳を鍛えてこなかったのであれば、一気に片付けをすることなど不可能でしょう。
間違えて必要な物も捨ててしまう可能性があります。
捨てる脳を鍛えるためには、小さなエリアでよいので、少しずつ捨てて片付けをしていくことです。
買い物をするときも、まずはどうやって捨てるかを考えることです。
毎日少しずつ、捨てること・片づけることをやっていきましょう。
まとめ:物を捨てて快適空間を目指そう

物をため込む人の心理と捨てられる人になる方法を紹介してきました。
「私は捨てるのが苦手」と思わずに、少しずつ捨てること・片づけることをしていってください。
そうすれば誰でも、捨てられる人になりますよ。
「物を捨てて快適な生活をしよう!」と決心したあなたは、捨てる基準を紹介しているこの記事を読んでみてください。
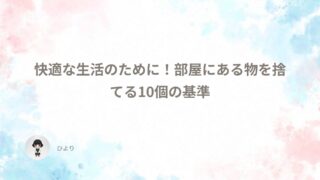
捨てる基準に当てはまるかどうかを確認するだけで、家が片付いていきます。
ぜひ、捨てる作業をやってみてください。
おしまい